―健康とサプリメントの
基礎知識―
“なんとなく良さそう”から、“よく分かって使う”へ。
あなたの健康づくりを、正しい知識でサポートします。
・第3回:健康食品の制度と表示のウラ側
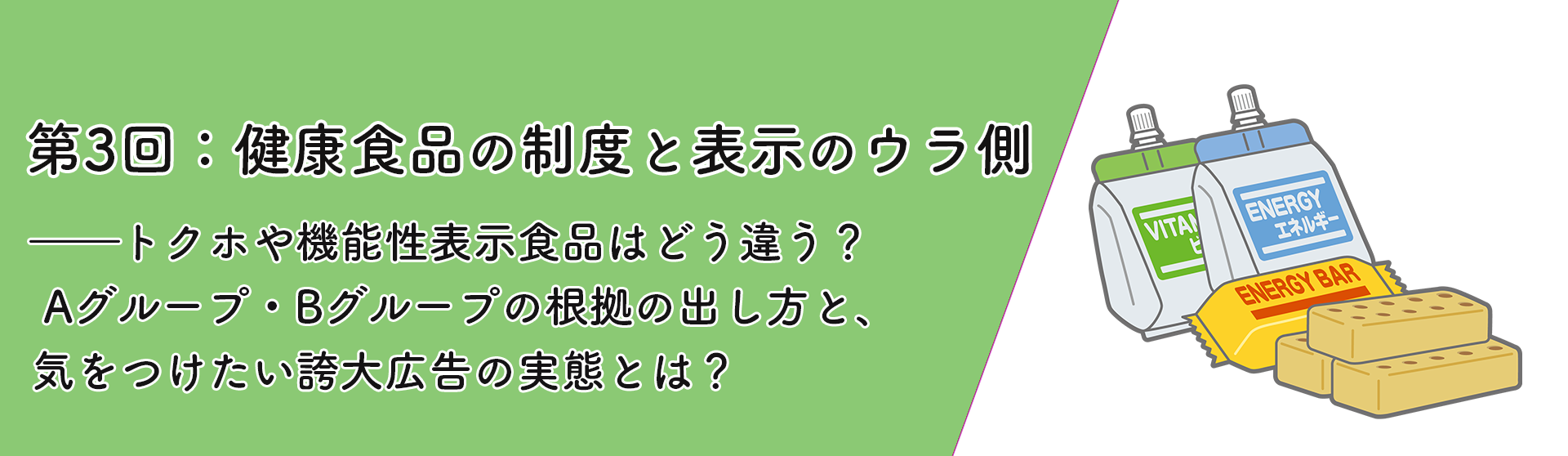
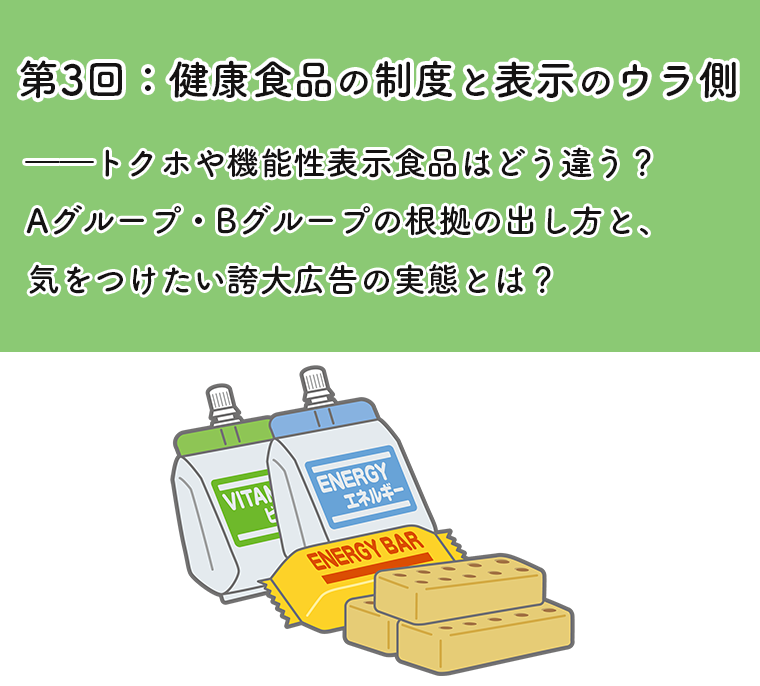
1. 健康食品の表示制度とは
「健康食品」と呼ばれるものには、国が制度を設けて“機能”や“効果”を表示できるものと、そうでないものがあります。
消費者庁が定める制度の下で表示が認められているものを「保健機能食品」と呼び、以下の3種類があります。
- ・特定保健用食品(トクホ):国の審査と許可を受けている
- ・栄養機能食品:定められた栄養成分について基準を満たせば表示可能
- ・機能性表示食品:企業が科学的根拠を示し、消費者庁へ届出をすれば表示可能(ただし国の審査はなし)
一方で、こうした制度に入らない「いわゆる健康食品」には、効果効能を表示することはできません。
2. 機能性表示食品の“根拠の出し方”
機能性表示食品は、企業が責任を持って「科学的根拠」を示す必要があります。 その根拠の出し方は大きく2つに分けられ、AグループとBグループと呼ばれています。
-
・Aグループ(研究レビュー型)すでに発表されている研究論文を集め、システマティックレビューを行って根拠とする方法。
多くの機能性表示食品がこの方式を採用しています。 -
・Bグループ(自社臨床試験型)企業が自社でヒト臨床試験を行い、その結果を根拠とする方法。
製品ごとの独自性をアピールできますが、試験設計や信頼性の評価が重要になります。
健康食品の分類(Aグループ・Bグループ)
下表はWeb掲載向けに、Aグループ(制度に基づくもの)とBグループ(その他)の区分を、代表例・特徴・注意点で整理したものです。
| グループ | 区分 | 主な食品例 | 特徴・表示 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
|
Aグループ
(制度対象)
|
特別用途食品 | 病者用(低たんぱく、低カロリー等)、介護食、乳児用調整粉乳 | 対象者別に栄養設計。医師や管理栄養士の指示で利用される。 | 一般向けではない。誤用に注意。 |
| 特定保健用食品(トクホ) | 整腸作用をうたうヨーグルト、血圧対応飲料など | 国の審査・許可を受け、特定の機能を表示できる。 | 薬ではない。効果は個人差あり。 | |
| 機能性表示食品 | 脂肪吸収抑制サプリ、血糖値対応のお茶、目の疲労軽減サプリ | 事業者が科学的根拠を示して届出することで表示が可能。 | 消費者庁は個別審査を行わない。根拠の質に差あり。 | |
|
Bグループ
(その他)
|
栄養補助食品 | マルチビタミン、鉄やカルシウム等の単体サプリ、プロテイン | 日常の食事で不足しがちな栄養を補う目的。 | 上限量を超える過剰摂取に注意。 |
| ハーブ・植物由来 | ウコン、アロエ、青汁(植物由来)、漢方原料を含む健康食品 | 伝統的利用や植物由来の機能訴求が多い。 | 科学的根拠は限定的。相互作用に注意。 | |
| 動物由来 | ローヤルゼリー、プロポリス、コラーゲン含有食品 | 美容・エイジングケア目的の製品が多い。 | アレルギーや品質差に注意。 | |
| 発酵食品系 | 乳酸菌飲料、納豆菌サプリ、麹(こうじ)由来食品 | 腸内環境や発酵由来成分の訴求が特徴。 | 菌種・配合量で効果は大きく変わる。 | |
| 機能訴求系(一般) | 酵素食品、健康茶、ダイエット補助食品 | 多様な機能をうたうが根拠はさまざま。 | 誇大表示や過度な期待に注意。 | |
| その他一般食品 | 加工食品や飲料の中の健康訴求商品(ラベルで訴求) | 通常の食品扱い。栄養表示や加工表示の確認を。 | 表示読み取りに慣れると選びやすい。 |
← スクロールできます →
医薬品と食品の大まかな違い(要点)
以下は図をテキストで置き換えた要約です。医薬品は病気の診断・治療が目的で承認制度があります。食品は基本的に栄養補助・健康維持を目的とし、治療を目的にできません。
- 医療用医薬品(処方薬):医師の診断で処方。病気の治療が目的。
- 一般用医薬品(OTC):薬局等で購入可。軽度症状の対処・予防が目的。第1類〜第3類がある。
- 特別用途食品:乳児用、病者用、妊産婦用など、対象者別に設計。
- 保健機能食品:特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品など。
- 機能性表示食品:事業者が根拠を示して届出する。
- 一般食品:通常の食品、サプリメント、健康茶など。
注:ここでは制度の詳細や手続きは省略しています。制度を説明する際は原典(消費者庁等)を参照してください。
3. 気をつけたい表示や広告
- ・これを飲めば病気が治る」といった効能表示はNG
- ・「医師も推薦!」「奇跡の天然成分!」などの誇大広告には注意
- ・消費者庁の制度を利用していない製品は表示内容の信頼性に差がある
健康食品の広告の中には、法律で認められていない表現や誇大な宣伝が紛れています。 「効きそう」「安心そう」という印象だけで判断すると、思わぬ健康被害や治療の遅れにつながることもあります。
4. 表示を見極めるために
- ・「トクホ」「栄養機能食品」「機能性表示食品」のどれに当たるか確認
- ・機能性表示食品は“国の審査ではなく、企業の責任”という点を理解する
- ・情報の出典や根拠が示されているかチェックする
表示制度を理解しておくことは、商品の信頼性を見極める第一歩です。
とくに機能性表示食品は国の“お墨付き”ではないことを知り、広告表現や表示内容を冷静に読み解く力を持ちましょう。
■まとめ
健康食品の中には国の制度に基づいて機能を表示できる「保健機能食品」があります。
とくに機能性表示食品は、Aグループ(研究レビュー型)とBグループ(臨床試験型)の2通りの方法で根拠が示されます。
しかし、表示されているからといってすべてが安全・確実とは限りません。
制度を理解し、誇大広告に惑わされないようにすることが、消費者自身の健康を守る力につながります。